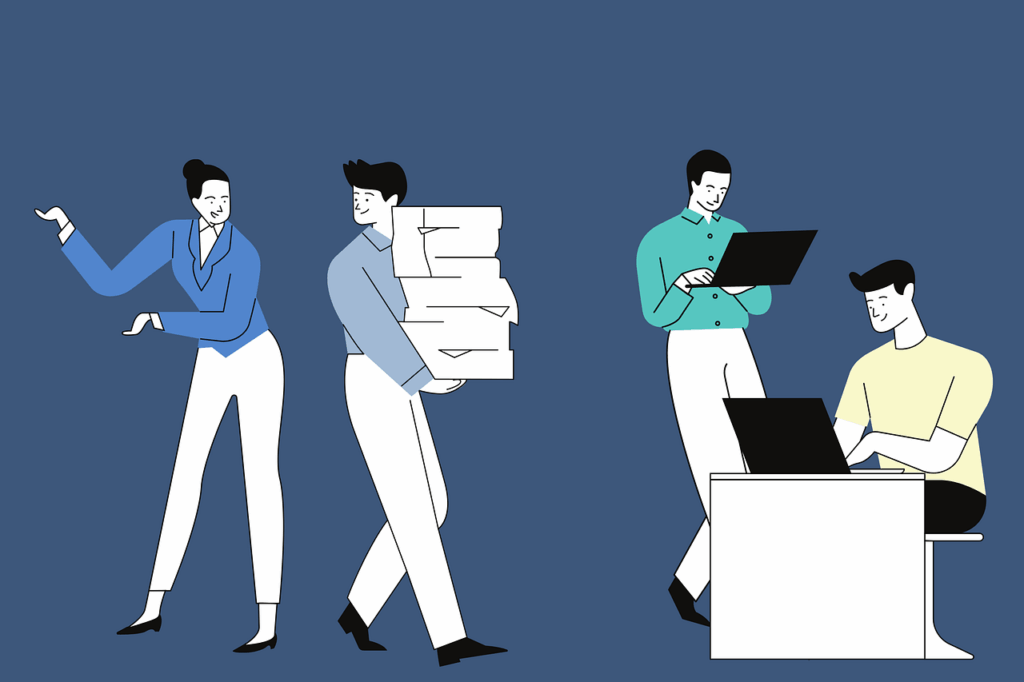
目次
一般社団法人の理事会とは
今回は一般社団法人の『理事会』について解説します。
理事会については設置するしないも含めて、一般社団法人の設立時にしっかりと理解しておく必要があります。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』
そもそも理事会とは
『理事会』とは全理事によって構成され、業務執行に関する意思決定を行う機関です。(設置するかは任意)
「うーん、何となくは分かるけど社員総会と何が違うの?」と思われるかもしれません。
そこで理事会を分かりやすくするために、『社員総会との違い』と『理事会のメリットデメリット』という2点から見ていきましょう。
社員総会との違い
『社員総会』とは、一般社団法人の『最高意思決定機関』です。
社員総会は議決権を持つ社員で構成され、法人の重要事項について決議します。
詳しくはこちら➡︎『一般社団法人の社員総会とは』
一方『理事会』は、業務執行に関する意思決定を行う機関です。
理事会を設置しない法人では、法人の重要事項の『全て』を『社員総会』にて決定します。
理事会を設置する法人では、『一部の事項』を『理事会』にて決定することができます。
つまり、理事会を設置すれば、全ての事項に関して、いちいち社員総会を開かなくても良いことになります。
それでは理事会で決定することができる『一部の事項』とは何でしょうか?
それは『法律や定款で規定している事項以外』の事項となります。
「法律(一般法人法)で規定されている事項」と「定款にて定めた事項」以外は、理事会にて業務執行の意思決定をすることができます。
「法律(一般法人法)で規定されている事項」は以下のようになっております。
法律で規定されている事項
・役員の選任、解任
・役員の報酬
・定款の変更
・事業譲渡
・解散
・合併
その他の事項は定款で定めることにより社員総会での決議事項とできますが、定めなければ理事会での決議事項となります。
理事会の決議
理事会では原則、議決に加わることができる理事の過半数が出席して、その過半数で決議を行います。
なお、定款にてより厳しい要件とすることも可能です。
また、理事会の決議では特別利害関係者となる理事は議決に参加できません。
以上のことから、理事会を設置した場合は『より業務執行の意思決定がしやすくなる』といえます。
理事会のメリットデメリット
理事会のメリット
理事会のメリットは先述したものとなりますが、『法人の業務執行の意思決定がしやすくなる』という点になります。
ある程度規模の大きな一般社団法人では社員の数が多くなり、全国に分散していることもよくあります。
そうなると、何かを決める際にいちいち社員総会を開いていたのでは、あまり効率はよくありません。
そこで理事会を設置し、特に重要な事項以外は理事会で意思決定を行うことで、スムーズな法人運営が可能となります。
理事会のデメリット
次に理事会のデメリットとしては、『理事によって、法人の意思決定が行われてしまう』という点かと思います。
メリットと裏表の関係となりますが、「社員総会を開く必要がない」ということは「社員総会を開かなくても意思決定ができる」ということになります。
それを防ぐためには『定款にて理事会の決議事項を制限しておく』必要があります。
法人にとって『どこまで理事会で意思決定するのか』をはっきりさせておかないと、後々トラブルの元となりかねません。
その他、理事会について
理事会の設置要件
理事会には以下の設置要件があります。
理事会の設置要件
・理事が3名以上必要
・監事が1名以上必要
となりますので、ある程度の規模の法人でないと設置できないでしょう。
また監事とは、法人の財産や理事の業務執行を監査する役職のことです。
理事会には監事も出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければいけません。
理事会の開催頻度
理事会は、原則、3ヶ月に1回のペースで開催しなければいけません。
ただし定款に定めた場合は、年2回の開催まで減らすこともできます。
理事会の招集
理事会の招集は、原則、各理事が行います。(定款で別の定めを規定することも可能です。)
招集権者は、理事会の日の1週間前までに、各理事に通知を発します。(定款の定めにより、期間を短くすることも可能です。)
ただし、理事監事全員の同意がある時は、開催手続きを省略して開催することができます。
業務の執行
理事会は業務執行の意思決定を行いますが、実際に業務を執行するのは『代表理事』と『業務執行理事』です。
『業務執行理事』とは、理事会において業務を執行するよう選定された理事です。
それ以外の理事は、業務は執行しませんので、理事会を構成するメンバーということになります。
ですので、『意思決定は理事会』で『業務執行は代表理事と業務執行理事』という関係がなりたちますが、全ての意思決定のたびに理事会を開くのは現実的ではありません。
そこで、理事会は『代表理事』と『業務執行理事』に、一定程度の意思決定を委任することができます。
ただし、以下の重要な事項については委任することはできません。
委任できない事項(簡易表現版)
・重要財産の処分、譲り受け
・重要使用人の選任、解任
・多額の借財
・法令等に適合する体制の整備
・従たる事務所その他の重要な組織の設置や変更、廃止
・理事等の損害賠償責任の免除
また、理事会は職務執行が意思決定に基づいて、適切に行われていることを監督しなければいけません。
そのため代表理事と業務執行理事は、3ヶ月に1回以上の頻度で、理事会に業務の遂行状況について報告する必要があります。
なお定款に定めた場合は、報告の頻度を『事業年度内に4ヵ月を超える間隔で2回以上報告』とすることもできます。
代表理事、業務執行理事の選定
理事会は『代表理事』と『業務執行理事』を、理事の中から選定することができます。
この両理事については、業務執行権限がありますが、どちらでもない平理事は業務執行権限はありません。
また、職務執行が不適切と判断した場合は、理事会は両理事を解職することができます。
オンラインでの開催
理事会はZOOM等のシステムを利用し、オンラインでも開催することができます。
ただし、『出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境』が必要となります。
出席者全員の通信状態に支障がなく、映像・音声が問題なく相互に意見交換できることを確認しておきましょう。
また、議事録には『WEB会議システムを用いて理事会を開催した旨』や、『WEB会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認されてから、議案の審議に入った旨』を記載する必要があります。
理事会の決議省略
理事会の場合も、社員総会同様に決議を省略できます。(みなし決議)
以下の要件が必要となります。
決議省略の要件
・定款に決議の省略ができることを記載。
・事案について理事全員の同意があること。
・書面または電磁的記録により同意すること。
・監事の反対がないこと。
社員総会の場合は、定款に定めなくとも決議の省略が可能ですが、理事会の場合は定款に定めておく必要があります。
また、理事全員の同意とありますが、特別利害関係者となる理事の同意は不要となります。(元々参加できないため。)
全員の同意が得られる場合は、わざわざ理事会を開かなくとも良くなりますので、定款にはこの定めを入れておいたほうがよいでしょう。
なお、決議省略する場合も議事録の作成は必要となります。
まとめ
以上、一般社団法人の『理事会』について見てきました。
ある程度規模の大きな一般社団法人の場合は、理事会を設置した方がスムーズな運営が可能になるかと思います。
ただし、理事会についてしっかりと理解して設置する必要があります。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』



