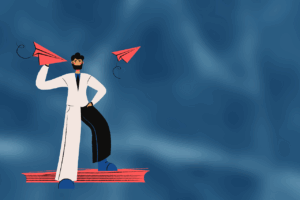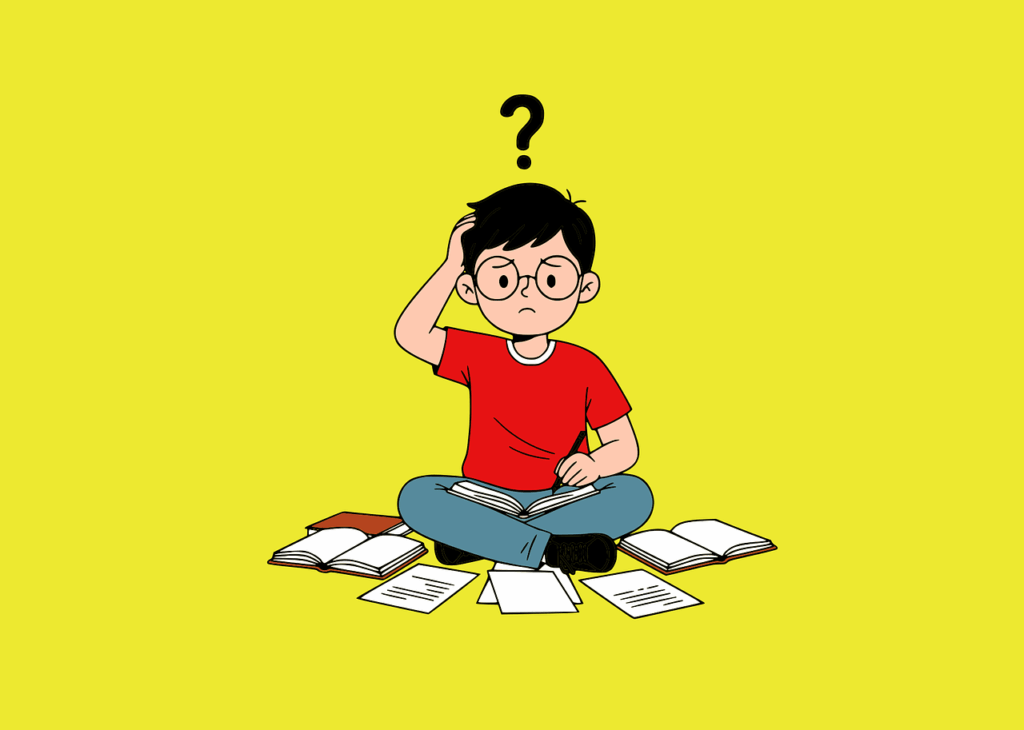
目次
一般社団法人の非営利型について分かりやすく解説します
今回は一般社団法人の『非営利型』について、分かりやすく解説していきます。
一般社団法人を設立する際に、多くの人が疑問に思う『非営利型』ですが、しっかりと理解すれば、概念自体はそこまで難しいものではありません。
『非営利型』について、しっかりと理解しておきましょう。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』
非営利とは
まずは『一般社団法人における非営利』について解説します。
実は一般社団法人における『非営利』と『非営利型』は別の概念となります。
ここを混同してしまうと、よく分からなくなりますので、ここでは『非営利』と『非営利型』は別のものだという認識を持ちましょう。
非営利とは
一般社団法人における非営利とは、『余剰利益を社員に分配できない』ということです。
「ん、どういう意味?」と思われたかもしれませんが、この概念も分かりにくいので、情報の整理が必要です。
もう少し分かりやすく解説していきます。
※一般社団法人でいう『社員』とは、いわゆる従業員のことではありません。株式会社でいうところの『株主』に似た存在で、株主総会にあたる『社員総会』で議決権を持つ者のことです。重要な立場の者とイメージしてください。
余剰利益とは
まず、余剰利益について解説します。
余剰利益とは簡単にいうと『事業を行い、決算の結果、余ったお金』のことです。
さらに簡単にいうと『1年事業を行い、最終的に余ったお金』ということです。
事業を行うには、通常は従業員等に『給与』を支払う必要があります。
これは一般社団法人の場合でも同じです。
ですので、余剰利益も『給与等を支払った上でさらに余ったお金』ということになります。
『余剰利益を社員に分配できない』と聞くと、「給与も払えないのか?」と思うかもしれませんが、そうではありません。
役員報酬や従業員への給与、ボーナスなど、労働の対価として正当の価額を支払うことができます。
その点は株式会社等となんら変わりません。
分配できないとは
分配できないとは、『給与やボーナスとは別に、余ったお金を社員に配ることができない』ということです。
株式会社の場合は、余ったお金を株主に分配することができます。
いわゆる配当というものです。
一般社団法人はこの配当のような行為が社員に対してできないということです。
利益を出すことは可能
また、ここまでの話の前提となりますが、一般社団法人は『利益を出すことは可能』です。
一般社団法人における『非営利』とは、『余剰利益を社員に分配できない』という点のみでの話となります。
イメージ的には「非営利なので利益を出してはいけない。ボランティア事業でないといけない。」と思いがちですが、そうではありません。
また、余剰利益はどうするかというと、翌年度以降の法人の活動資金にあてられるということになります。
この活動資金にはもちろん『給与』も含まれます。
まとめますと以下のようになります。
一般社団法人の非営利とは
・利益を出すことはOK
・役員や従業員に給与を支給することはOK
・余剰利益を社員に分配することはNG
・余剰利益は翌年度以降の活動資金となる
余談ですが、株式会社の場合でも、余剰利益を配当することは少ないかと思います。
大きな会社や特殊な事情がある場合は別ですが、配当を行いますと税務上不利になることが多いですので、あまり配当はしないケースが多いと思われます。
株式会社でも中小規模の会社は、配当するよりも翌年度の給与をアップしたり、事業拡大の資金としたりすることの方が多いのが実情です。
非営利型とは
それでは本題の一般社団法人の『非営利型』について解説します。
一般社団法人には『非営利型』と『普通型』があります。
これはあくまで『税法上の区分』の話になります。
ですので、利益を出す出さないとか、配当できないという話とは関係なく、『税金』面での話になります。
税法上の非営利型とは
では税法上の『非営利型』とは、具体的にどういうことでしょうか。
それは『収益事業での所得(利益)のみが、課税の対象となる』ということです。
つまり、収益事業での所得には課税されて、収益事業以外での所得には課税されないということになります。
では『収益事業』とは何でしょうか?
余談ですが、『所得』と『利益』という言葉の違いについて簡単に説明しておきます。
まず概念として『会計』と『税務(税法)』の2つは別物だという認識が必要です。
会計は、簡単にいうと会社の財政状況を把握するためのもの。
税務は、税金を納めるためのものです。
この2つは、同じ結果となることもあれば、少し違う結果となることもあります。
ですので、『用語』も違う言葉を使うことがあります。
今回でいえば、会計上の利益は『利益』、税務上の利益は『所得』という言葉になります。
『課税対象』という言葉を使用する時は、税務上の話ですので『所得』という言葉を使います。
ですので上記のような表現をしていますが、ざっくりと理解するだけなら、どちらもいわゆる『利益』を指していると思っていただいて問題ありません。
収益事業とは
収益事業とは、法人税法に定められた34種類の事業のことを指します。
具体的には以下の事業のことですが、営業行為のほとんどが該当することになります。(その性質上その事業に付随して行われる行為を含みます。)
①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑥製造業、⑦通信業、⑧運送業、⑨倉庫業、⑩請負業、⑪印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理店業その他の飲食店業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業、㉑鉱業、㉒土石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊技所業、㉘遊覧所業、㉙医療保健業、㉚技芸教授業、㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝無体財産権提供業、㉞労働者派遣業
法人税法2十三、法人税法施行令5①
実務上は、寄付金や会費などは収益事業とはなりませんが、その他ほとんどの事業は収益事業となります。
ただし、サービスの対価として会費を徴収する場合は、会費も収益事業となる可能性があります。
何が収益事業とならないかの判断は難しいものがありますので、自己判断せずに税務署に事前に確認するようにしましょう。
税金面で優位になる
ということで、『非営利型』の一般社団法人であれば、寄付金や会費などの所得に対しては課税されない可能性がありますので、税金面で優位となります。
寄付金や会費が見込める場合には、『非営利型』を選択するのも良いでしょう。
ただ、ほとんどの事業は収益事業となりますので、その点は注意しておきましょう。
収益事業メインとなる予定であれば『普通型』でも良いと思います。
普通型とは
『普通型』の場合は、寄付金や会費に対しても課税されます。
これは株式会社等と変わりません。
全ての所得に対して課税されます。
非営利型の一般社団法人となるには
それでは、どうやったら『非営利型の一般社団法人となれるか』について解説します。
『非営利型』となるには、いくつかの形式上の要件を満たす必要があります。
ただし、形式上の要件を満たしていたとしても、実際に『非営利型』として認められるかは、税務署の判断となります。
実際に法人の実態が非営利型として認められるかについては、慎重な判断が求められますので、顧問税理士や税務署に確認しながら、法人を運営していく必要があります。
非営利型となる2つのタイプ
非営利型と認められるには2つのタイプがあります。
以下の2つのタイプです。
①非営利性が徹底された法人
②共益的活動を目的とする法人
それぞれ解説していきますが、どちらのタイプを選択するかは法人の目的によって決めると良いでしょう。
どちらのタイプがよいか?
どちらのタイプが良いかですが、絶対的な答えがあるわけではないので、簡単には選択できないかと思います。
それぞれの『特徴』を把握して、法人の目的や活動に合致する方を選びましょう。
非営利性が徹底された法人の特徴
『非営利性が徹底された法人』の特徴ですが、以下のものとなります。
・収益事業を法人の主たる事業とできる。
・法人を解散したときは、残余財産を国や地方公共団体など公益性の高い団体に帰属させること。
最も大きな特徴は、収益事業を主たる事業とできる点でしょうか。
先ほど、『非営利』の説明で、一般社団法人も利益を上げることができると話しました。
しかし、次に説明する『共益的活動を目的とする法人』は、収益事業を主たる事業とできないという特徴があります。
(主たる事業とは最も収入が多い事業のことです。)
その点こちらのタイプは、『普通型』同様に収益事業を主たる事業とできますので、運営の自由度が高いといえます。
仮に設立当初は「会費メイン」で運営を行う予定でも、途中から収益事業も積極的に行なっていく可能性もあります。
将来的な可能性も考えると、こちらのタイプを選択するほうが無難ともいえます。
法人を解散した時の残余財産の帰属先にも制限がありますので、ここも把握しておく必要があります。
一般的には、福祉関係など社会貢献度の高い『事業』を行なっていきたい時に選ばれるタイプとなります。
共益的活動を目的とする法人
『共益的活動を目的とする法人』の特徴ですが、以下のものとなります。
・会員の相互の利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
・主たる事業として収益事業を行っていないこと。
・残余財産の帰属先が特定の個人や法人であると定款に定めないこと。
こちらは会員の相互の利益を図ることが、主たる目的となっていますので、いわゆる「業界団体」や「地域団体」などが想定されます。
また、主たる事業として収益事業を行えませんので、この制限は大きな特徴といえます。
残余財産の帰属先の制限については、こちらの方が少し緩く、社員や会員に帰属できる可能性が残るタイプです。
一般的には、業界団体など会費収入がメインとなる場合に選ばれるタイプといえます。
非営利性が徹底された法人の要件
それでは、『非営利性が徹底された法人』の形式的要件を見ていきましょう。
以下の内容となっております。(分かりやすいように簡易的に要約した文となります。)
非営利性が徹底された法人の要件
1.定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること
2.定款に解散時に残余財産を国や地方公共団体など公益性の高い団体に帰属させる旨を記載していること
3.上記1及び2の定款の定めに反する行為を実際に行っていないこと
4.理事の親族等の割合が、理事の総数の3分の1以下であること
それぞれ解説します。
※ここでは「剰余金」と、先述した「余剰利益」は、同じものとお考えください。
1.定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること
定款に剰余金を分配しないことの記載が必要となります。
ただ、そもそも一般社団法人は『剰余金の分配』は禁止なので、そのような要件をここで求める必要があるのでしょうか?
実は、一般社団法人でいう非営利の『剰余金の分配の対象者』は社員となります。
ですので、特定の団体や個人などの社員以外に対しても剰余金の分配を禁止するために、このような記載が必要となります。
2.残余財産を公益性の高い団体に帰属
法人が解散した時の残余財産の帰属先を、国や地方公共団体など公益性の高い団体とする旨を定款に記載する必要があります。
余剰金を分配しないという非営利性の趣旨を守るため、解散時の残余財産の帰属先についても、定款で定めておくことを求められます。
3.1及び2の定款の定めに反する行為を実際に行っていないこと
この項目では、1と2の項目を実態として守ることを求められています。
また、『特定の個人または団体に、特別の利益を与える』ことも禁止されています。
『特別の利益』が何を指すのかに関しては非常に判断が難しいのですが、イメージとしては特定の者に対して不相当に高い(安い)金額で取引を行うこと等です。
例えば、『過大な役員報酬を支払っていたり』、『理事の所有する物件を過大な金額で賃借したり』することなどです。
これを許してしまうと『剰余金の分配』と変わらない行為となってしまい、1と2の項目を守っていないことになります。
何を持って『過大(過小)』とするかは判断が難しいところですので、税務署や税理士へ相談するなど注意が必要です。
また、もしこの項目に反したと判断された場合、その法人は2度と非営利型になれませんので気をつけましょう。
4.理事の親族等の割合が、理事の総数の3分の1以下であること
この項目は、親族等による法人の私物化を防ぐための項目です。
非営利型は適正な組織であることを求められますので、関係の強い親族等の人数に制限がかけられています。
『3分の1以下』となっていますので、まず理事の総数が『3人以上』必要です。(理事会の設置は必須ではありません。)
理事が3人の場合は、全員が他人でないといけません。
もし、2名の親族がいる場合は(例えば夫婦)、理事は全員で6名以上いる必要があります。
常に親族等が理事総数の3分の1以下である状態を保つようにしましょう。
また、様々な事情により3分の1を超える状態となった時は、相当の期間内に再び3分の1以下となるようにすれば、すぐに非営利型でなくなるということはありません。
それでは『親族等』とはどのような関係者なのかも見ておきましょう。
以下が『親族等』とされます。
親族等
・理事の配偶者
・理事の3親等以内の親族
・理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係)
・理事の使用人
・1から4までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
・3から5までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
このように、範囲が広いので注意が必要です。
※3親等以内の親族とは、本人及び配偶者を0親等とし、3つ移動した親族までのことです。父母は1親等、祖父母は2親等、兄弟は2親等といった具合です。(配偶者の父母等も同じ扱い)
※使用人とは、一般的に法人と雇用契約を結ぶ者や、指揮命令系統に入っている者のことです。
共益的活動を目的とする法人の要件
次に、『共益的活動を目的とする法人』の形式的要件を見ていきましょう。
以下の内容となっております。(分かりやすいように簡易的に要約した文となります。)
共益的活動を目的とする法人の要件
1.会員の相互の利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
2.定款等に会費の定めがあること
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
5.解散時に残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定款に定めていないこと
6.上記1から5まで及び下記7に掲げる要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
7.理事の親族等の割合が、理事の総数の3分の1以下であること
それぞれ解説します。
要件7については、非営利性が徹底された法人と同様となります。
1.会員の相互の利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
定款の目的の条文に、会員の相互の利益を図る活動を主たる目的として記載する必要があります。
相互の利益を図る活動が主たる目的ということで、『業界団体』や『地域団体』といった組織が想定されます。
2.定款等に会費の定めがあること
定款等に会費に関する定めを記載しておく必要があります。
一般的には定款で具体的金額を定めるのではなく、『別途規定により定める』等と記載し、その別途規定で具体的な金額等を定めることが多いかと思います。
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと
先述しましたが、主たる事業として収益事業を行うことができません。
一般的には『会費』の収入が最も多い組織となるかと思います。
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
『定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと』ですので、定款でわざわざそのような事を記載しなければOKです。
先ほどの『非営利性が徹底された法人』では、分配しない旨の記載が必要でしたが、ここでは分配する記載がなければ良いですので、先ほどよりは少し緩い制限という印象です。
5.解散時に残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定款に定めていないこと
この項目も4と同様に、定款にそのような記載をしなければOKです。
なお、6でも説明しますが、社員に残余財産を帰属させることを定めることはできませんが、社員総会の決議の結果、社員に残余財産を帰属させることはできます。
『非営利性が徹底された法人』の場合は、社員に帰属させないように定款で帰属先を定めることになっていますので、その点は少し緩くなっています。
6.上記1から5まで及び下記7に〜
『上記1から5まで及び下記7に掲げる要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと』とありますので、『非営利性が徹底された法人』同様に、実態として1〜5を遵守する必要があります。
また、『非営利性が徹底された法人』と同様に、『特定の個人または団体に、特別の利益を与える』ことも禁止されています。
ただし、『非営利性が徹底された法人』と違うのは、『残余財産の帰属』に関しては除外されているという点です。
『共益的活動を目的とする法人』の場合は、『会費』が収入のメインとなることが想定されますので、その会費を解散時に社員や会員に還元することまでは規制しないと考えられます。
まとめ
今回は一般社団法人の『非営利型』について、見てきました。
『非営利型』の概念自体はそこまで難しいものではありませんが、要件などは複雑で難解だったかと思います。
また、実際に非営利型と認められるには形式上の要件だけでなく、実態として非営利型を遵守する必要があります。
一般社団法人の設立後も、税務署や顧問税理士に確認しながら運営を行なっていきましょう。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』